英語長文の勉強法
入試で出題される英語長文の難化が著しく,総語数が増えて語彙のレベルも上がっています。GMARCH の英語長文問題で合格ラインに達するのは容易なことではありません。まして最難関国公私立大学ともなれば,そのハードルの高さは誰もが実感しているはずです。よほどしっかりした手順で,しかも効率良く勉強していかないと,つまり正しい勉強法を見につけていないと,望む結果は得られません。そこで「英語長文の勉強法:英語長文の読み方と問題の解き方」を掲載しました。
英語長文の読み方と問題の解き方
[1] 英語長文を速く正確に読む方法
1 外国語である英語の文章を速く正確に読むためには,一定レベルの文法・構文の知識(読解文法)が不可欠です。背景知識の有無も重要です。そして最初にして最後の決め手は単語力でしょう。パラグラフ・リーディングをはじめ,スキミングだリーズニングだと,様々な技法が喧伝されてきました。設問を解く際にこうしたテクニックが必要なケースがあることは否定しませんが,さすがに今どき,各パラグラフの最初と最後のセンテンスだけを読んでいく「パラリー」なるテクニックが通用すると思っている人はいないでしょう。とはいえ,頭の中で日本語に置き換えることなく,段落を手掛かりに英文の内容(筆者の主張)を追っていくのは容易なことではありません。そこに至る前提として以下のプロセスが必要です。
2 英語長文に取り組む前提として,①単語と熟語を記憶する,②文法を理解・記憶する,③構文を理解・記憶する,この三つのプロセスが必要です。実際にはこの三つは切り離されたプロセスではなく,同時に進行してくものです。 なお, 数行の英文を精読する,いわゆる英文解釈であっても,英文全体の内容(主張)を把握することが大切です。いっぽう英語長文読解においてもこの三つのプロセスが繰り返されることに変わりはありません。長文読解では,限られた時間で筆者の主張の展開を追うために速読が求められますが,だからといって精読が不要になるわけではありません。
3 ①の単語については「英単語の覚え方」を参考にしてください。②の文法に関しては「重要英語文法解説」をご覧ください。③の構文は,項目別の文法とは差別化を図り,改訂版の「重要英語構文 大学受験」で体系的に取り上げています。改定に伴い,英語の各例文に日本語訳と詳細な解説を付したのでご覧ください。 昨今「暗記から理解へ」と称して, 理解さえすれば覚える必要はなくなる, という奇妙な主張を見かけますが, 理解を知識として定着させるには「記憶」という作業が不可欠なことは言うまでもありません。 暗記というネガティブに聞こえる言葉を意図的に用いて, 記憶という人間の知的な営みに不可欠のプロセスを阻害する短絡的な主張に惑わされてはいけません。
4 英文を「速く」「正確に」読むために,返り読みをせず,英語を英語の語順のまま日本語を介在させずに読む速読速解が必要になりますが,その最も効果的な方法がスラッシュ・リーディングであり,音読であるとされています。スラッシュ・リーディングには根強いファンがいますが,スラッシュの入れ方については人によって言うことが大きく異なります。またスラッシュ・リーディングは依存症になります。試験に限らず,英文を見たら新聞・雑誌・書籍を問わず片端からスラッシュを引かないと英語が読めなくなります。あるいは読むスピードが著しく遅くなります。ところが実際には,頻繁にスラシュを入れる手間暇だけで長文を読むスピードが遅くなり,速読速解の妨げになります。一定レベル以上の読解力が身につくと,そのことに気がつきます。
5 センテンスが長い場合に適宜スラッシュを入れていくことを一概に否定しませんが,意味の固まりを把握できてはじめてスラッシュを入れられるわけですから,間違えて入れたスラッシュに縛られて,文構造も意味内容も掴めなくなるのは本末転倒です。スラッシュの必要があるとすれば,英語の書き言葉はカンマの使い方が恣意的で,書き手によって著しく異なるからです。つまり本来あるべきなのに存在しないカンマの代わりにスラッシュを入れていくわけです。その場合も,英文をなるべく大きな意味の固まりで捉える練習をしましょう。要するに,スラッシュが不要になることが,高度な読解力が身についた証なのです。まだそのレベルに達していない人も,挿入語句節や修飾語句節をカッコで括っていくほうが,英文の構造や意味内容を掴みやすと思います。

6 同時通訳方式と称して,数語ずつ,意味の固まりごとに前から日本語に訳していくことをスラッシュ・リーディングと呼ぶ人がいます。しかしこの方法を「英語の速読速解」と言うのは無理があります。このやり方が役に立つのは, 基本的な文法や構文の知識が欠けていて, 英語長文の速読力どころか短文の精読力もまだ身についていないレベルの人にとってです。 しかし,構文が複雑で内容も難解な英文を,いっさい日本語を介さずに英語の語順のまま正確に読むことが出来るのは,教養ある英語ネイティブに近い高度なバイリンガルくらいでしょう。だから短期間に読解力を飛躍的に伸ばすには,2 で挙げた三つのプロセスを,多様な英文を読みながら行っていく必要があるのです。
7 次は音読についてです。驚くことに,英語は黙読よりも音読のほうが速く読めると思っている人がいます。日本語であれ外国語であれ,黙読のほうがはるかに速いことは言うまでもありません,音読を重ねると黙読のスピードも増すのは事実ですが,音読そのものは,正確に読めるレベルに達した英文を確実に身につけるための復習の方法です。以下に阿佐谷英語塾の英語コンテンツ「リスニング&音読用英文」の冒頭に記載した注意書きを掲載します。
・英文の単語・文法・構文・内容を理解して,正確に読める状態にします。
・この過程をスキップすると誤聴と誤読の集積になります。
・その後で YouTubeなどの動画で音声を再生します。
・読めない英語を聴いても音読しても,内容を聞き取る力も読む力も身につきません。
・音が聞き取れることと内容が聞き取れることはイコールではありません。
・初めは英文を見ながら音声を聞きます。慣れてくると音声だけで聞き取れるようになります。
・正確に聞き取れる英語を,正確に発声(音読)することで,書く力を含む総合的な英語力が身につきます。
*現在一部の動画が著作権の問題等で削除され, 視聴できなくなっています。
8 実は音読についても様々な考えがあります。一つのパッセージを三度は音読することを薦めるのは穏当なアドバイスです。実際には30-40回はおろか60-70回をマストとする意見さえあります。これは完璧に暗唱することを薦めていることになります。インプットする英文の数と量が少ないうちはそれほど負担にはなりませんが,入試英語の長文化に伴って英文の総量が増えてくると, 相当な時間と労力を費やすことになります。 しかも, 学習環境にもよりますが, 音読は黙読と違って何時でも何処でもできる作業ではありません。 さらには, 音読が自己目的化する恐れもあります。あくまでも聴解力と読解力をつけるための音読ですから,費やす時間や労力と効果とのバランスを忘れないことです。
9 「リスニング&音読用英文」は,元がスピーチ(演説)等の音声だったものを文字起こしして音読にも使えるようにしたものです。しかしリスニング用の音源としても,海外帰国生や留学経験者,あるいは一部の大学を受験するリスニングの得意な人以外には,あまり取り組みやすくないと思います。そこで, 元が書き言葉である「英語長文」を音声化することを考えました。 つまり speech to text ではなく text to speech です。一度に読み上げる text の語数を調整しながら,最終的には1500語超えの長文でも音声化することが可能です。これが可能になったのは,声優の声を使った AI による音声合成が飛躍的に進歩したからです。ソフトにもよりますが,男女数人の声優の中から選べて,スピードも声のトーンも変えられるので,生の人間が吹き込んだCDと遜色がないどころか,むしろ優れていると言えるかもしれません。
10 ただし, テレワーク等の影響でパソコンを使う人が増えたとはいえ,スマホが多数派であることに変わりはありません。 幅の狭い iPhone の画面で文字を追っていくのは容易ではないかもしれません。実は text to speech の最大のネックは, 使い勝手の良い音声再生の仕組みを埋め込むことと, 高性能な音声読み上げソフトを入手することです。この問題を完全にクリアーしたた訳ではありませんが,新たなコンテンツとして「リスニング&音読用英文 英語長文」 をアップロードし(2022.12.8), AI による音声に修正を加えてかなり聞き取りやすくしました(2023.10.16)。 ほとんどの人にとって,「外国語」である英文を音声だけで追うのは, 音声とテキストの両方で追うよりもはるかにハードルが高いのは事実です。 しかし途中の段階で, 耳と目を使って英文の内容を追うことが, 読解力の向上に資することは言うまでもありません。 相当な速度で, 返り読みをせずに目で追う練習になるからです。
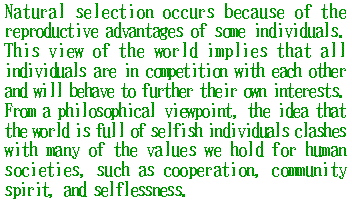
[2] 英語長文問題の解き方
1 英語長文問題に取り組む際にまずやるべきことが二つあります。一つはごく常識的なことであり,ほとんどの人が実際に行っていると思いますが,本文を読み始める前に設問に目を通すことです。下線部や空所の前後を読むだけで答えられる設問と,例えば「表題選択」や「内容真偽」のように本文全体を正確に読まないと答えられない設問があるからです。もう一つは各段落に番号をふっていくことです。慶應経済,慶應SFC,2021年までの早稲田法学部のように,出題されたときからパラグラフに番号が付いている大学・学部もあります。パラグラフに番号をふる理由は,段落を意識して論旨の展開を追っていくためです。 と同時に, 設問と本文を照合する際に該当する段落をマークするためです。
2 英語長文の論旨の展開を追うためには,文章の主題と,その主題に対する筆者の基本的な立場を早めに掴むことが大切です。これを掴んだ上で接続詞・接続語と代名詞に注意して文脈を追っていくことが必要です。前後の文を対等の関係でつなぐ等位接続詞 (and, but, or, for, so) と, 主節を修飾する副詞節を導く従位接続詞 (when, if, because, though, although, since, as), そしてあくまでも副詞である接続語 (however, nevertheless, therefore, moreover) の区別がつかない人がいます。この違いが分らなければ,難関大学レベルの英語を正確に読むことも, 空所補充問題に対処することも出来ません。一方,精読の名の下に構文を偏重する人に共通するのが,代名詞を軽視していることです。they は主語,them は目的語くらいは誰でも分かりますが,それが何を受けているかによって,英文の内容は大きく異なるにもかかわらず,その意識が希薄です。
3 英文の論旨(論理)の展開はけっしてワンパターンではありません。第一段落の最初のセンテンスで主題と同時に結論までが提示されている場合もあれば,第一段落,ときには第二段落の最後のセンテスで主題が明らかになる場合もあります。段落が変わって論旨が展開していくときも,内容的には段落改行は必ずしも必要ない程度のこともあれば,段落と共に主題が大きく転換していくこともあります。入試に出題される英文も名文ばかりとはいかず,駄文・悪文も少なくありません。ときにはパッセージの途中で主題が大きく変化して,前半の内容は刺身のツマにさえならない場合もあります。したがって,英語の文章構成には基本的な一つのパターンがあり,それを理解していればあらゆる英文の内容を追えるかのような思い込みは, むしろ弊害となります。
4 実際には,日本語の文章と同様,論旨の展開が論理的でない英文のほうがむしろ多数派と言えるでしょう。論理の飛躍・矛盾に限らず,冗長,重複,逸脱,事実に反する記述も珍しくありません。おそらく具体的な例を挙げなければ分らないと思われるので一例を挙げます。 (更新に伴い, より分かりやすい例に差し替えました。)
生物の左右対称と非対称 (symmetry and asymmetry) という興味深いテーマを扱ったパッセージ(高3 SA76 大阪大学後期)です。 第二段落に以下の記述があります。 Try turning your hands palm side up and looking at the veins in your wrists that are carrying blood back to the heart. You'll notice that the pattern of spacing of these veins in one wrist is an approximate mirror-image of the pattern in the other wrist「手の平を上に向けて,血液を心臓に送り返している両手首の静脈を見てみよう。片方の手首の静脈の間隔の空き方が,もう一方の手首の静脈の間隔の空き方とおおよそ左右対称であることに気づくだろう」しかし全訳の後に補足した通り, 左右の手首の静脈の形状の対称性などは元々存在しないものです。もしかすると筆者自身は希有な例外で, こうした記述がおおよそ当てはまるのかもしれませんが。
英文の内容とは別に, そもそも英語表現として疑問符のつく例も珍しくありません。 実は英文の内容と英語表現の両方に疑義のある例も少なからずあります。 一昔前に比べると, この種の英文は増加傾向にあると思われます。 AI の飛躍的な進歩に反比例するかのように, 人間の論理的で明晰な思考が衰退しているのではないかと危惧されます。
5 残念ながら, 予測に反して自動翻訳は簡単に進歩しません。 Google 翻訳に勝ると言われる DeepL(ディープエル) や ChatGPT も, かなり複雑な構文を読み取れても単純な文脈を読めないことがあります。 細部の表現は脇に置くとしても, 未だ完全に信頼できるレベルからは相当な距離があります。 これについて二例を挙げます。 一例目は, 心理学と脳神経科学の研究者の立場から通説に異を唱えるたいへん興味深いパッセージ(高3 SA97 大阪大学前期)です。
第七段落下線部(1)の DeepL の訳です。 A slammed door, rather than a fish tank, may well be the best candidate for a loud bang if, for example, there is a strong breeze blowing through a nearby window, or if your heartbroken lover has just stormed out of the room and you've experienced similar exits in past relationships. 「例えば, 近くの窓から強い風が吹いていたり, 失恋した恋人が部屋から飛び出してきたばかりで, 過去の恋愛で同じような出方をした経験がある場合は, 水槽ではなく, バタンと閉まったドアが大きな音を出す最適な候補になるかもしれない」DeepL は has just stormed out of the room を「部屋から飛び出してきたばかり」と訳しています。 文脈上「部屋から飛び出していったばかり」が正しいことは言うまでもありませんが, stormed out of the room を stormed out of the room to the corridor とでもしなければ訂正されません。
二例目は, なぜこの英文を訳せないのかと思う事例です(高3 AD15 東工大)。 第一段落全文の DeepL の訳です。 For most of human history, creativity was regarded as the power of supreme beings. All religions are based on origin myths in which one or more gods shaped the heavens, the earth, and the waters. Somewhere along the line they also created men and women ─ weak, helpless things subject to the anger of the gods. It was only recently in the history of the human race that the tables were turned: men and women were now the creators, and gods the products of their imagination.「人類の歴史の大部分において, 創造性は至高の存在の力とみなされてきた。すべての宗教は, 一人または複数の神々が天と地と水を形作ったという起源神話に基づいている。神々の怒りにさらされる弱く無力な存在である。男女が創造主となり, 神々は想像の産物となったのだ」
第一文と第二文は問題ありませんが, 第三文と第四文は壊滅的です。 第三文は along the line が理解できず, また weak helpless things がmen and women の言い換えであることが掴めなかったのでしょうか。 第四文はまさか強調構文が分からないことはあり得ませんから, the tables were turned を知らなかったのでしょうか。 以下に阿佐谷英語塾の訳を付しておきます。「人間の歴史の大部分において, 創造力は至高の存在である神々が持つ力と見なされていた。 あらゆる宗教は, この世の起源に関する神話に基づいているが, そうした神話では, 一人あるいは複数の神が天と地と海を形作ったとされている。 この天地創造の過程のどこかで, 神々は人間の男と女も創ったのだが, 人間は神々の怒りに触れやすい, 弱く無力な存在だった。 人類の歴史上, 最近になってはじめて形勢が逆転した。 いまや人間が創造主であり, そして神々は人間の想像力の産物であった」
AI の飛躍的な進歩により, 人間の本質的な属性である言語の習得が不要になる日がやって来るのどうかは分かりません。 しかし, 言語の獲得は人類最大の謎だと言っても過言ではありません。 囲碁や将棋, 自動運転やロボットと異なり, 近い種来 AI による自動翻訳が人間の頭脳を超える可能性が高くない以上, まだ当分の間は外国語の学習が不要になることはないでしょう。

(次回の更新をもって完結します)
6 単語・イディオムの問題に取り組む手順
7 下線部和訳問題に取り組む手順
8 要約・説明問題に取り組む手順
9 内容真偽問題に取り組む手順
10 表題選択問題に取り組む手順